みなさんはご自宅に災害時の備蓄、きちんとされていますか?
「ばっちりしている」という方も、
「非常食、賞味期限切れちゃって…」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、災害時の「食の備え」について考えます。
わが家の「ゆる防災」体験記
災害用のものを用意するというと、
どうしたらいいか迷ってしまいます。
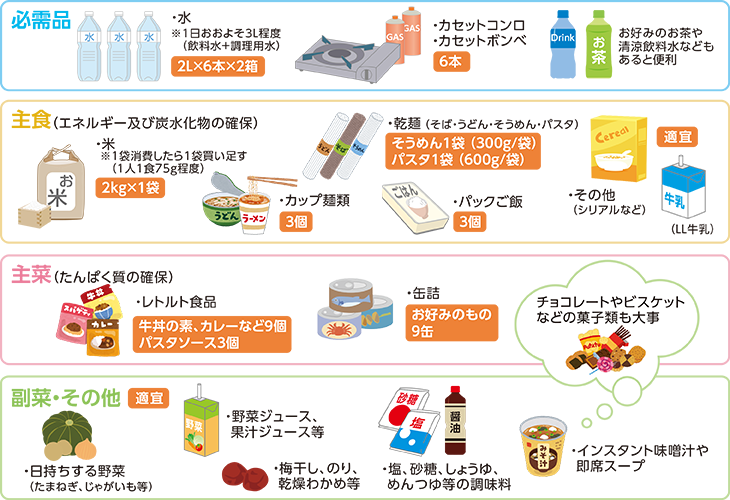
上の表は、「大人1人の1週間分の備蓄例」です。
農林水産省のホームページから引用しています。
家族の人数や年齢を考えると、
それに応じた食材が必要になります。
わが家では、年に1〜2回「災害時を想定した生活」を取り入れています。
この生活を実際にすると、
自分の家には何が足りていないのか、気づくことができます。
「ゆる防災」の設定

あらかじめ、どういう設定でするのか決めます。
- 電気は使わない(冷蔵庫は電源を落とさず、あくまで「使わない」という設定)
- 水は備蓄用のペットボトルを使用
- 調理は火だけ(コンロを使用)
- エアコンは使用してもOK
たったこれだけのルールですが、
実際にやってみると、電気や水の大切さを実感します。
夕食作り

午後7時頃になると、部屋の中はだいぶ暗くなります。
携帯ラジオやランタンの明かりだけが頼りです。
夕食は暗くなる前に準備しました。
冷蔵庫に残っていたうどんと、
備蓄していたインスタント麺を茹でることにしました。

2歳の娘には、そのまま食べられるレトルトカレー用意するつもりでした。
が、見つかりません。
どうやら以前食べていたようです。
普段からよく使っている魚の缶詰も、
ストックを切らしていました。
いつもなら「まあ、また今度買えばいいか」で済ませていたことが、
いざという時には「ないと困る」という気持ちになります。

冷蔵庫にあった「もずく」や、
オートミールを使いながら夕食は完成です。
必要だと思う食材

実際に、災害時を想定した生活をすると、
何が使えて、普段から何を準備しておけばいいかよくわかります。
わが家で必要なものは以下のようなものです。
✓ 子ども用のそのまま食べられるレトルト食品
✓ ツナ缶や魚の缶詰のローリングストック
✓ オートミールやナッツ、レーズンなどの私の好物
✓ インスタント食品
「日常的に消費する食材を、少し多めにストックしておく」
ローリングストックの大切さを今回改めて痛感しました。
一番むずかしいこと
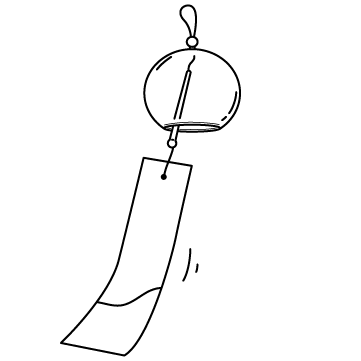
このゆる防災生活をしていつも感じることがあります。
それは「夏の涼をとるのは大変だ」ということです。
40度近く気温が上がる中、
エアコンなしで生活するのはとても困難です。
とくに2歳の娘はすぐに汗をかき、あせもができてしまいます。
夏場の熱中症対策をどうすればいいのか・・・。
大きな課題です。
まとめ
今回は、災害時の「食の備え」について考えました。
いろんな団体のホームページで、
備えるべきものは紹介されています。
それを参考にしつつ、
「実際に災害時を想定した生活」をやってみることが
一番大切だと思います。
今回の「ゆる防災生活」でも、
自分自身気付いたことが多々ありました。
皆さんの普段からしている工夫などあれば、
教えていただけると幸いです。




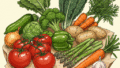
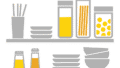
コメント